シルクロードに関する多彩なトピックを、貴重書アーカイブの資料を織り交ぜつつ、北京大学・考古文博学院の林梅村教授を中心とするシルクロード研究者に紹介していただきます。
中世ペルシア湾の古代海港―シラフ港の発見―黄珊 (北京大学考古文博学院修士課程)シラフ(Siraf)は中世ペルシア湾の有名な港で、イランのブシェール省(Bushehr)南部のタヒリ(Tahiri)村以西1.5マイル(約0.93km)に位置する。中世期、ペルシア湾に向かう東方の船舶は多くの場合海岸線に沿って航行し、ほとんどの船はペルシア湾に入って北岸のシラフ港で品物の積み卸しをおこない、一部の船はさらに北上しメソポタミア地方、すなわちチグリス・ユーフラテス川河口のウラ港(現在のイラク、バスラ付近)に至った[1]。ペルシアとアラブ帝国の初期、シラフはペルシアとインド、中国との海上貿易の重要な拠点の一つとなった。977年の大地震により、栄華を極めたこの古い港も凋落の一途をたどり、13世紀初めには完全に放棄された[2]。この大地震の後、ホルムズ海峡西端に位置するキシュ島(Kish Is.)のホルムズ港が次第にペルシア湾の最も主要な港の一つになっていった。マルコポーロと鄭和率いる明朝海軍艦隊はどちらもホルムズ港に上陸しており、この時シラフ港はすでに忘却の彼方にあった。 一、中国内外の関連史籍唐代から広州には市舶使がおかれ、東南海路の対外貿易を統括した[3]。広州、シラフ間の海上交通のルートについては『新唐書』地理志に詳しい記録がある。この航路は広州から出発してベトナム、タイ、マレーシア、インドネシア、マラッカ海峡、スリランカ、インド、パキスタンを経由してペルシア湾に入り、シラフを通って最後にイラクのバスラに到達する。北京大学の林梅村教授は、この航路上にあらわれる「提羅盧和国」がシラフ港のことだと考えている。盧和とはイランのファルス省東南部のLar地区のことで、別名「羅和異国」とも称し、アラビア語のLarwiにあたる[4]。唐・徳宗期の宰相(『通典』の作者)杜佑に、杜環という族子があったが、不幸にしてタラスの役で大食(タージー)軍の捕虜になり、中東諸国を十数年流浪し、唐宝応元年(762)にペルシア湾から商船に乗って広州に戻った[5]。杜環がペルシア湾で乗船した港こそ、『新唐書』地理志に言及されている「烏剌」港(現在のイラク、バスラ付近)、あるいは「提羅盧和国」つまりシラフ港であろう。9世紀中葉にアラブの作家によって描写されたペルシア湾から中国までの航路は、『新唐書』地理志の述べるところとほぼ一致する[6]。 唐末から宋代にかけて中国を訪れたアラブ商人のうち、多数を占めていたのはシラフ人であった[7]。彼らは海路、広州に至り、後に泉州などの沿海都市にも広がっていった。南宋・岳珂『桯史』には泉州に「尸羅圍」という商人がいたことが、南宋・趙汝適『諸藩志』には「施那幃」という大食商人がいたことが記されている[8]。日本の桑原騭蔵は、この両者ともShilaviの音訳で、「シラフ人」の意味であると解している [9]。10世紀初めにシラフ港に居住していたアラブ作家のアブ・ザイード・ハッサン(Abu Zaid Hassan)は、黄巣の乱について次のように記している。「国中の無数の県城を攻め落とした後、ヒジュラ歴264年(878年・唐僖宗乾符五年)に康府(Kanfu、すなわち広州)を攻め落とした。中国事情に詳しい人物によると、中国人のほか回教徒、ユダヤ人、キリスト教徒、ゾロアスター教徒もまた多く殺されたという。この戦いで死んだものは12万人……中国の動乱は万里の波頭を越え西拉甫港(つまりシラフ)と瓮蛮(今のオマーン)両地の人にまで影響した[10]。」 二、シラフ港の発見シラフ港廃址は、1835年にインド海軍船長ケンプソーン(Kempthorne)がタヒリを通りかかった際に初めて発見された[11]。1933年、英国人スタイン(M.A. Stein)は、第4次中央アジア探検において、中国の地方政府により国外退去の憂き目にあったため計画の変更を余儀なくされ、中央アジアとイランの探検を行った。このイラン探検時に、スタインは初めてシラフ港の考古学的調査を行った[12]。 このペルシア湾の古港は、山脈によって居住区と墓地とが隔てられている(シラフ港遺跡平面図(図 1))。山には至るところに住居址が見られるが、その性質は不明で、家屋の土台と壁がわずかに残るのみである(シラフ港住居跡の壁(図 2))。墓地は主にシラウ谷(Shilau)に集中している。スタインはシラフ遺跡の居住区で、大型の独立した建造物を発見した。それらのうち主要なものを以下に記す。
1. 防波堤:シラフ遺跡の壁はすべて加工されていない石を積んでつくられ、石膏あるいは漆喰が塗られている。海に面して延々と続く約450ヤード(411.3m)の防波堤(シラフ港の防波堤(図 3))があり、現存する高さは約15フィート(4.5m)で、これも同様の方式で作られている。防波堤の外壁には馬面が残り、多くは三角形で、半円形のものもある。波の浸蝕を防ぐ為のものだろう。その基礎部分から発見された土器片は遺跡区のものと同種で、遺跡と同時期に建てられたものと思われる。
2.「チーク材柱のモスク」:防波堤の西端には大型の建築遺跡が残っている。南北約55ヤード(50.2m)、幅約25ヤード(22.85m)で、地震により崩れたものと思われる(シラフ港遺跡平面図:B (図 1))。遺跡には大量の石と土塊がふくまれ、漆喰を塗った約2~3ヤード(0.6~0.9m)の長方形の大きな石の柱座が見られる。スタインはここが文献に出てくる「チーク材柱のモスク」であると推測した。チーク材は南アジアと東南アジアの特産品であり、これも海運貿易を反映するものであろう。 3.臨海建築物:遺跡西部の海に面した入り江に42ヤード(38.39m)四方の閉鎖式建築物があり、海に面した東壁には一辺が19.5フィート(5.85m)の三角形の馬面が四つ残っている(臨海建築物遺跡(図 4))。この遺跡の性質は不明だが、石の加工技術と付近から採取された土器片から見て、遺跡と同時期のものと考えられる。 4.後期モスク:山脈の西部は丘陵地帯で、遺跡を二つに隔てている。丘陵南面には古い建造物がそびえ立ち、一部は外壁の巨大な土台の上に建てられている(モスク遺跡(図 5))。これはモスクで、遺跡内の他の建造物に比べて保存状態がよく、天井板や壁面に残る幾何学模様の装飾図案が描かれた漆喰から見て、15、16世纪をさかのぼることはないと思われる。 5.後期マドラサ:海抜約125フィート(37.5m)の尾根上に四角形の建築物があり、現地ではマドラサ(madrasa、イスラム学校)と呼ばれている(マドラサ遺跡(図 6))。残存する漆喰と窓の上枠から発見された木片からみて、年代はやや下るものと思われる。
シラフ遺跡の主要な墓地はシラウ谷にあり、谷底から海抜300フィート(90m)の中腹まで数百基の石穴墓が密集している(シラウ谷墓地全景左側(図 7)、シラウ谷墓地全景右側(図 8))。シラフ港は重要な国際貿易港で、人口も多く、民族と宗教の内容も複雑で、葬送儀礼の上にも明確に反映されている。 墓地西部の緩やかな山肌には、墓がグループごとに規則的に並んでいる(シラウ谷墓地西部(図 9))。なかには伝統的な南北方向からずれるものもあるが、圧倒的多数は依然として伝統を守っており、ここもムスリムの墓地とみて間違いあるまい。
このほかに後期モスク遺跡の西と南の断崖上にも石穴墓が並んでおり、スタインは高所で比較的年代が早く荒らされていない墓をムスリム墓と判断している。同じ山肌には6、7件の墓碑がみられ、その多くに古代アラビア文字が刻まれている(シラフ出土アラビア文字墓碑(図 10))。1978年、中国海南島三亜市送路で唐代のアラブ文字の墓碑((図 11))が発見された。そこには「万物に主なし、ムハンマドのみがアラーの使者」というイスラムの箴言が書かれていた。同様の墓が三亜市送路、酸梅角と陵水県干教坡でも発見され、総計は50余りにのぼる[13]。これらは客死した異郷のムスリムで、大部分はシラフ港から中国に来たペルシアあるいはアラブの商人である。
元代以降、蒲寿庚の一族は泉州に海外貿易基地をつくった。唐代の広州~シラフ間の東西海上交通もまた、泉州~ホルムズ間の海上交通に取って代わられた[14]。 この墓地の東部の墓はすべて東西方向に並んでいる。スタインの統計によると、この区域には375基の墓があるが大部分が空っぽで、壊れた蓋板が少量残るだけである。厚さ4~5インチの砂岩の壁で仕切っているものもあり、また墓と墓の間には小さな空間が設けられており、そこに児童が埋葬されている。こうしたことから、この墓地の墓は計画的に並べられ、特に経済的要素が考慮されていることが知られる。このような埋葬方式は他の場所ではみられず、ここが非イスラム集団のための専用墓地だったことを示している。東西方向に埋葬する風習は沿海のユダヤ人集団で流行していたことから、この墓地の主人はシラフに居住するユダヤ人であったと考えられる。 シラウ峡谷北側の崖上にはハチの巣状の浅い洞穴がみられる。その多くは天然の洞窟で、スタインはそのうち粗い加工痕が残る二つの洞窟を調査している。一つは人骨と思われる指骨と趾骨が二つ発見されただけで、別の一つには塵芥と散乱した石以外なにもなかった。スタインはこれらの天然洞穴は当時人骨を安置するために使用されたのではないかと推測している。あるいはペルシアのゾロアスター教の葬送儀礼に従い、禽獣が死者の肉体を食い尽くした後に骨を持ち帰り、洞穴に安置したもので、「天葬」と呼ぶべきものかもしれない。 878年の黄巣軍による広州での外国人商人虐殺に関するアラブ作家の記録によると、被害にあった外国人商人は「回教徒、ユダヤ人、キリスト教徒、ゾロアスター教徒」で、「万里の波頭を越え西拉甫港(シラフ)と瓮蛮(現在のオマーン)両地の人々に影響した」 [15]という。シラフ港のアラブ人とユダヤ人墓地の発見は、アラブ作家の記録が史実であることを証明している。 シラフ港で発見された陶磁器のうち、とりわけ人目を引くのが長沙窯の輸出用磁器である。9世紀のアラブ商人蘇来曼(Sulaimān)の旅行記に、「商品はバスラ、オマーンとその他の地方からシラフ(Siraf)に運ばれ、大部分の中国船はここで荷積みする」と記されている[16]。考古学的発見により、唐が中東に輸出した商品は主に長沙窯の輸出用磁器であったことが知られている。例えばインドネシア各地からは唐代にインドネシアに運ばれたたくさんの長沙窯磁器が発見され、現在ジャカルタ国立博物館に収蔵されている(唐代長沙窯輸出用陶磁器(図 12))。1933年にスタインがシラフ遺跡で収集した陶磁器片のなかには唐代の長沙窯の製品がある(スタインがシラフ港遺跡で採集した中国磁器片(図 13))。1966~1972年、ホワイトハウスはシラフ遺跡において六回の大規模な発掘を行い、そのうち五カ所で長沙窯輸出用磁器が大量に発見された[17]。これらの発見は、当時の中国~ペルシア湾地域間の海上交通と貿易について研究するうえで重要な材料を提供するものといえる。 (付記:挿図11・挿図12は林梅村先生の提供によるものである。ここに謹んで謝意を表したい。)
[1] 三上次男著、李錫経、高喜美訳『陶磁之路』(北京、文物出版社、1984年)89-93頁。
[2] M.A. Stein, Archaeological Reconnaissance in North-Western India and South-Eastern Iran , London, 1937, pp. 202-212.
[3] 『旧唐書』玄宗上、開元二年十二月乙丑、「時右威衛中郎将周慶立為安南市舶使、与波斯僧広造奇器、将以進内;監選使、殿中侍御使柳澤上書諫、上嘉納之」。
[4] 林梅村『絲綢之路考古十五講』(北京、北京大学出版社、2006年)229頁。
[5] 杜佑『通典』卷一九三『辺防典』引杜環『経行紀』。
[6] 穆根来、汶江、黄倬漢訳『中国印度見聞録』(北京、中華書局、1983年)7-10頁。伊本・胡爾達茲比赫著、宋峴訳注『道里邦国志』(北京:中華書局、1991年)63-75頁。
[7] 桑原隲蔵著、陳裕菁訳『蒲寿庚考』(上海、中華書局、1929年)140-141頁。
[8] 南宋・岳珂『桯史』巻十一・番禺海獠、呉企明点校(北京、中華書局、1981年)127頁。南宋・趙汝適『諸蕃志』巻上、引自王云五『叢書集成初編』(上海、商務印書館、1937年)16頁。
[9] 桑原隲蔵著、陳裕菁訳『蒲寿庚考』(上海、中華書局、1929年)140-141頁。
[10] 張星烺『中西交通史料』第二冊(北京、中華書局、1977年版)207-208頁。
[11] G.B. Kempthorne, Transactions of the Bombay Geographical Society, vol. XIII,1856-1857, pp.125-129.
[12] M.A. Stein, Archaeological Reconnaissance in North-Western India and South-Eastern Iran , London, 1937, pp. 202-212.
[13] 広東省文管会等単位編『南海絲綢之路文物図集』(広州、広東科技出版社、1991年)54頁。
[14] 呉文良、呉幼雄『泉州宗教石刻』増訂本(北京、科学出版社、2005年)。
[15] 張星烺『中西交通史料』第二冊(北京、中華書局、1977年版)207-208頁。
[16] 穆根来、汶江、黄倬漢訳『中国印度見聞録』(北京、中華書局、1983年)7頁。
[17] D. Whitehouse, “Excavations at Siraf: First Interim Report,” Iran, vol. 6, 1968, pp.1-22; D. Whitehouse, “Excavations at Siraf: Third Interim Report,” Iran, vol. 6, 1970, pp.1-18; D. Whitehouse, “Excavations at Siraf: Forth Interim Report,” Iran, vol. 9, 1971, pp.1-17; D. Whitehouse, “Excavations at Siraf: Fifth Interim Report,” Iran,vol. 9,1972,pp.62-87; D. Whitehouse, “Some Chinese and Islamic Pottery from Siraf,” Pottery and Metalwork in Tang China, London, 1972, pp. 30-34.
2007年2月28日 発行
翻訳: 篠原 典生
編集: 大西 磨希子
|
目次執筆者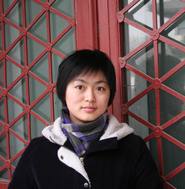 1984年、湖北省漢川市に生まれる。2002年に北京大学考古文博学院入学。2006年に卒業し、歴史学学士の学位を取得。卒業論文の題目は『「紅海航行記」と漢代海上交通』。現在、北京大学考古文博学院修士課程に在籍。研究テーマは、宋元時代の中国と西方の海上交通。
[
もっと詳しく...
]
索引ディジタル・シルクロードおことわり
|
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。












