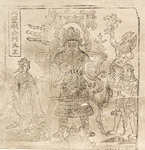シルクロードに関する多彩なトピックを、貴重書アーカイブの資料を織り交ぜつつ、北京大学・考古文博学院の林梅村教授を中心とするシルクロード研究者に紹介していただきます。
毘沙門天の発見篠原典生 (北京大学考古文博学院博士課程)仏教寺院を訪れると、山門を入ってすぐの建物の中に甲冑を身にまとい恐ろしい形相で見下ろしてくる四体の仏像に気がつく。彼らは仏教の護法神で、四天王と呼ばれている。四天王は帝釈天につかえ、それぞれ須弥山の東西南北の門を守るものとされ、それぞれ持国天、広目天、増長天、多聞天という名前を持つ。四天王像は一般に甲冑を身にまとい、剣や戟などの武器を持ち、足下に邪鬼を踏みしく武将の姿であらわされ、寺院の金堂や本堂などの須弥壇、また寺院の入り口を守る四天王殿や石窟の前室などに四人一組であらわれることが多い(四天王像(挿図 1))。この四天王の中で、北方を守る多聞天は別名を毘沙門天といい、単独の神格としても篤く信仰を集め、中国大陸から日本列島に至る広い地域で多くの毘沙門天像が制作されている(トゥルファン交河古城出土の唐代毘沙門天麻布画(挿図 2))[1]。
毘沙門天を含む四天王の起源は仏教成立以前のインドに求められる。古代インドの四大ヴェーダの一つ、アタルヴァ・ヴェーダ(Atharva-Veda)やマハーバーラタ(Mahabharat)などに出てくる四方を守る神々が仏教に取り入れられ、四天王となった。四天王像の最古の例は、インドのバールフトにある仏塔の周りに配された石柱に残されている(紀元前2世紀頃)[2]。毘沙門天の前身であるこの北方を守る神はクーベラと呼ばれ、仏教経典では倶毘羅、金毘羅などと訳される。その姿は当時のインドの王侯貴族を模したものと考えられており、現在の毘沙門天の姿とはかなり異なっている。また、この頃は四天王像の姿にも大きな差異はなく、毘沙門天だけが特に信仰されていたような痕跡は見られない[3]。 毘沙門天に対する特別な信仰は、クシャン朝統治下のガンダーラで生まれた。ガンダーラはインド本土に対して北方にあたり、クシャン朝の王族は北方の守護神である毘沙門天を自分達の守護神として信仰した。それにともない、ガンダーラの毘沙門天は統治者であるクシャン貴族の姿、つまりイラン系のいでたちであらわされるようになった。ガンダーラ出土の浮き彫りには、インド系の衣服を纏った四天王の中で一人だけイラン系の着衣を身に着ける毘沙門天があらわされたものがあり、3~4世紀ごろのガンダーラでは毘沙門天に特別な地位が与えられていたことがわかる[4]。しかし、現在までのところ、ガンダーラ出土の仏像からは単独の毘沙門天像は確認されておらず、毘沙門天の独尊像は、パミールを越え、遠く中国に求められる。 初唐期にインドへ取経の旅に出た玄奘によって書かれた『大唐西域記』は、当時のシルクロードの地名や産物、風土などを現在に伝える貴重な文献資料であるが、そこに毘沙門天信仰に関する記述も見られる。それは瞿薩旦那国(クスターナ)の建国伝説である。瞿薩旦那国の王が子供がいないことを案じて毘沙門天廟で祈ったところ、毘沙門天像の額が割れて中から子供が出てきた。王は喜んでこの子を王宮に連れ帰ったが、この子が乳を飲まないので再度毘沙門天に祈ったところ、今度は地面がふくれて乳のようになり、子供はこれを飲んで成長したという。瞿薩旦那国はもともと毘沙門天が住んでいた場所であり、その王は毘沙門天の子孫であるという伝説がある[5]。この瞿薩旦那国とは于闐国(現在の新疆ホータン一帯)のことである。 七世紀前半、唐の太宗は西域経営に乗り出し、各地に新たな州や郡を設置していった。于闐に関しては、『新唐書』などの文献によると、貞観二十二年(648)に毘沙州が置かれ、上元二年(675)に毘沙都督府とされたという。しかし1930年に新疆で発見されたという「大唐毘沙郡将軍葉和之墓」碑(大唐毘沙郡将軍葉和之墓碑拓本(挿図 3))には「貞観十年九月三日」という日付が刻まれている。この墓碑によって、貞観十年(636)には、すでに毘沙郡が置かれていたことが知られる。毘沙郡の「毘沙」とは毘沙門天の略であり、毘沙門天が于闐国の建国神話に深く関わり、守護神として崇拝されていたことから、唐の行政機構も「毘沙」の名を冠することになった[6]。于闐国の毘沙門天信仰は、唐代には朝廷にまで広く知られていたのである。
20世紀初頭、スタインはホータン地区で調査、発掘を行い、多くの成果を上げた[7]。そうした遺跡のうち、ダンダン・ウィリク(「象牙の家々」の意)と呼ばれる仏教寺院遺跡で、上半身に鱗畳み、下半身は小札を綴った裾長の鎧を身にまとい、右手を腰に当て、少し腰をひねり、足下に邪鬼を踏む塑像が見つかっている(ダンダン・ウィリク塑像(挿図 4))[8]。頭部と左腕を失っているために、かぶり物や持ち物等はわからないが、その姿は確かに中国以東の地で見られる四天王像の姿によく似ており、スタインは『大唐西域記』の記述なども参考し、この塑像を毘沙門天像と見ている。敦煌石窟でも同型式の四天王像が多数制作され、石窟前室に置かれている(敦煌石窟第427窟(挿図 5))。他の天王像と非常によく似た形態を持つこの毘沙門天像を、便宜的に天王形毘沙門天像と呼ぶ。
同じくホータンのラワク遺跡からは、毘沙門天像に関してもう一つ非常に興味深い発見がされている。ラワク遺跡から見つかった塑像群のなかに、地中から半身をあらわした女形の地神に両足を支えられ、正面向きで裾長の服を着ている塑像がある(ラワク塑像(挿図 6))。上半身は失われているが、同じように地中から半身を出す地神に両足を支えられた毘沙門天像が、スタインやペリオらが敦煌から収集した敦煌画の中からも見つかっている(スタイン将来敦煌画(挿図 7))。
同型式の毘沙門天像は日本にも多くの図像や木彫像が残されており、代表的な作例としては、京都・東寺(教王護国寺)所蔵の木造毘沙門天立像があげられる。この毘沙門天像は「兜跋毘沙門天」という特殊な名称で呼ばれ、もと平安京の羅城門に安置されていたという伝承があり、安西城毘沙門伝説に由来する造像であることが知られている[9]。安西城毘沙門伝説とは、不空訳とされる『毘沙門儀軌』[10]に説かれている故事である。唐玄宗の天宝元年に安西城が賊軍に囲まれ、あわや陥落という急を知らせる報が長安に届いた。しかし、安西城は長安からあまりにも遠く離れているため、なすすべもない。その時、不空らの勧めで毘沙門天に祈ったところ、安西城に眷属を引き連れた毘沙門天が現れ、危機を救ったという説話である。この説話は遣唐使に従って入唐した留学僧らによって日本に伝えられ、これによって鎮護国家の神としての毘沙門天信仰が日本にも根付き、多くの毘沙門天像が将来、制作されることになった。研究者達は早くからこの特殊な毘沙門天像とラワク出土像の関係に注目し、「兜跋毘沙門天」の起源を西域に求めた[11]。いま、同型式の毘沙門天像を便宜的に「兜跋形毘沙門天」と呼ぶ。その特徴として、①半身をあらわす地天の両手に支えられていること、②裾長の西域式鎧をつけること、③宝塔を捧げ持つこと、④宝冠をかぶることなどがあげられる。 毘沙門天の両足を支えている地天については、『摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌』、『北方毘沙門天王隨軍護法儀軌』、『北方毘沙門天王隨軍護法眞言』、『吽迦陀野儀軌』などに典拠がある。中央の地天は、別名を歓喜天といい、左には尼藍婆、右には毘藍婆という二鬼がつき従うとされる。実際の作例では地天のみをあらわし、尼藍婆、毘藍婆はあらわされない場合もあり、ラワク出土像でも地天だけがあらわされているようであるが、地天に支えられて立つ姿は、天王形毘沙門天像と兜跋形毘沙門天像を区別する重要な要素となっている[12]。 裾長の鎧も、兜跋形毘沙門天像の特徴の一つである。天王形毘沙門天像は胸当てや獅噛等の中国式鎧を身につけることが多く、他の四天王と同様、唐の武将の姿を模したと考えられる。裾長の鎧は西域で流行したイラン系の武人の姿を模したとも言われるが(キジル石窟壁画武人像(挿図 8))[13]、遠くガンダーラの浮き彫りにあらわされた毘沙門天像にも小札を連ねた鎧を身につけるものがあり[14]、より異国的な雰囲気を醸し出しているといえる[15]。
ダンダン・ウィリク塑像は邪鬼を踏み手を腰に当て、体を少しひねる典型的な天王形毘沙門天像の特徴を有しているが、バールフトのクーベラ像も足下にヤクシャを踏んでおり、また鎧もガンダーラの浮き彫りに見られるものと同型式のもので、西方的色彩が強い。この図像が中原に伝わる過程で、基本的なスタイルは変わらず、しかし当時の武人が着けていた甲冑を身に纏うようになり、土着化していった結果、天王形毘沙門天として完成されていったのであろう。 一方、兜跋形毘沙門天像は、毘沙門天信仰と共に生まれたことが想像される。毘沙門天に対する信仰と、その信仰対象である図像とがセットで伝えられたために、その姿にも改変が加えられず、ほぼそのまま伝えられることになったのではないだろうか。「兜跋毘沙門天」という名称自体が、他の毘沙門天像とは異なる特別な存在であったことを示している。「兜跋毘沙門天」という名称は、現在までのところ中国大陸の毘沙門天像では使用例が確認されていない。しかし、敦煌石窟の壁画や、出土した仏画などには、明らかに兜跋形毘沙門天の特徴を有するものが少なからず発見されている。また最近の調査によって四川省や雲南省の7~9世紀頃の毘沙門天単独像が多く発見、紹介されているが、その多くが兜跋形毘沙門天像である事実は、この時期に毘沙門天信仰が中国各地に広まり、それと同時に兜跋形毘沙門天の図像も伝播していったことを示している(大足石窟北山第五窟(挿図 9))。
19世紀末から20世紀初頭の外国探検隊による中央アジア調査とその報告書の刊行により、それまで文献の伝承によるほかなかった「兜跋毘沙門天」に対する研究がホータンのラワク遺跡出土塑像、敦煌石窟の彫像、壁画及び仏画などの実例を得て飛躍的に進展した。松本榮一は、大著『燉煌画の研究』の中で、中国では「未だ兜跋毘沙門天像の遺例が発見せられて居ない」と記しているが、上記のように今日では中国各地で多くの作例が発見されている。100年前には外国探検隊が行った短期間の調査によって新資料が得られたが、現在は現地の研究者が時間をかけて長期的に調査を行い、すでに多くの調査報告が出されている。これらの新資料よって研究の新たな進展が期待される。 (注記:本文中に引用した図版のうち、挿図3は林梅村教授提供、挿図9は2005年に重慶市で開催された大足石窟国際学会の際に執筆者が撮影。特に記して感謝の意を表します。)
[1] 上方に「北方毘沙門天」との銘文がある。
[2] 現在はカルカッタのインド博物館所蔵。
[3] 宮治昭「インドの四天王と毘沙門天」(『毘沙門天像』日本の美術315、1992年)。
[4] 田辺勝美『毘沙門天像の誕生』、吉川弘文館、1999年。栗田功『ガンダーラ美術 I』、二玄社、1988年、図版238(四天王奉鉢図)。
[5] 唐・貞観二十年(646)『大唐西域記』巻十二、瞿薩旦那国の条。また、『大慈恩寺三蔵法師伝』巻五、瞿薩旦那国の条にも同様の記述が見られる。
[6] 薛宗正「大唐毘沙郡将軍葉和之墓考釈」(『新疆文物』1996年第3期)。林梅村「大唐毘沙郡将軍葉和墓表考証」(林梅村『古道西風』、三聯書店、2000年)。
[7] M.A. Stein, Ancient Khotan, London, 1907.
[8] 近年、新疆文物局等によってダンダン・ウィリクの再調査が行われたが、すでにこの塑像は失われていた。足下の邪鬼も頭部を失い、見るも無惨な姿になっている。したがって、スタインによって撮影されたこの写真だけが唯一の資料となってしまった。
[9] 東寺毘沙門天蔵の羅城門安置説に関しては、最近、岡田健氏が文献、美術史的に詳細な検討を加え、否定的な意見を発表している。岡田氏の論文は東寺毘沙門天像の研究史に対し批判的に検討を加え、詳しく分析しており、非常に有益である。岡田健「東寺毘沙門天像」上・下(『美術研究』第370・371号、1998・1999年)参照。
[10] 『大正蔵』第二十一巻。この教典は不空訳とされているが、説話中に不空自身が出現したり、『貞観釈経録』等にも収録されていないため、中国撰述経とみなされる。松本文三郎「兜跋毘沙門攷」(『東方学報』京都、第10冊第1分、1939年)参照。
[11] 源豊宗「兜跋毘沙門天像の起源」(『仏教美術』第15冊、1930年)。松本榮一「兜跋毘沙門天像の起源」(『国華』471号、1930年)。松本榮一(『敦煌画の研究』第九節「兜跋毘沙門天図」、東方文化研究所、1939年)。注10、松本文三郎「兜跋毘沙門攷」。STEIN, R.A., “Recherches sur l’épopée et le Bard au Tibet”, Paris, 1959.
[12] 兜跋毘沙門天と地天との関係については、松本榮一が『金剛明経』との関連を指摘している(注11、松本榮一『燉煌画の研究』)。また、北進一氏は土着の地母神である地天女と外来のサイノ神である毘沙門天の合体という観点から研究を行っている。北進一「兜跋毘沙門天の居ます風景」1~7(『自然と文化』52-58号、1996年)。
[13] 注11、松本榮一『敦煌画の研究』。
[14] 注4前掲栗田書の図版145、151(出城)。
[15] 兜跋毘沙門天像の甲制については、岡田健氏が注9論文で東寺像をとりあげ、裾長の鎧の上に胸当や獅噛等の中国式甲制をつける点に注目し、「唐時代に確立した中国的甲制と西域の要素とが融合されている点に最大の特徴がある」(下、71頁)と述べている。中国伝来以後の毘沙門天像の発展を考える上で非常に重要な指摘であるが、紙幅の関係上本文では触れられなかった。
2006年12月01日 発行
翻訳: 篠原 典生
編集: 大西 磨希子
|
目次執筆者 1977年東京生まれ。1996年9月、中国西北大学文博学院考古学専業入学、2000年7月卒業。2000年9月、北京大学考古文博学院修士課程入学、2003年7月卒業。現在、北京大学考古文博学院博士課程在籍。
[
もっと詳しく...
]
索引ディジタル・シルクロードおことわり
|
本ウェブサイトに掲載するデジタル文化資源の無断転載は固くお断りいたします。